黒は、心の深呼吸。
墨は、色というよりも「気配」です。紙の上に黒が立ち上がった瞬間、部屋の空気が一段落ち着く。奈良の老舗・古梅園(こばいえん)がつくる奈良墨は、その静けさの密度が違います。固形墨(墨)も、墨液も、ただ濃いだけではなく、線の端がきゅっと締まり、余白がすっと澄む。書道、写経、日本画、デザインのラフに至るまで、「黒で整える」人に長く選ばれてきた理由が、最初の一筆でわかります。
そして墨は、買って終わりではありません。すって、起こして、なじませる。黒を手の中で育てる時間まで含めて、ようやく一本の墨が完成します。古梅園の墨は、その「時間」を一緒に届けてくれるところが魅力です。

出典:古梅園
すって、黒を起こす。
当たり前ですが、固形墨は、そのままでは使えません。硯に水を一滴落とし、墨をゆっくり円を描くようにすっていくと、最初は薄い灰色が出てきます。そこから少しずつ、黒が「芯」を持ちはじめる。水を足しすぎると黒は痩せ、急ぐと黒は荒れます。だから、最初は水を増やさず、摩擦で黒を起こす。すると煤(すす)と膠(にかわ)がほどよく混ざり合い、線のキレ、止めの締まり、にじみの輪郭が安定してきます。
もうひとつ大事なのが、少し置くこと。すり上げた直後の墨は、まだ成分が落ち着いていません。ほんの数分でも寝かせると、黒がまとまり、紙の上で「思いどおりに働く黒」になります。墨は絵の具ではなく、呼吸のある素材。古梅園の墨が愛されるのは、この呼吸が、きちんと深いからです。

出典:古梅園
戦国の手紙にも、宮中の書にも、黒が要る。
戦国の朱印状にも、宮中の宸翰にも、黒が要る。紙の上で世界が動く時代ほど、墨の出来がそのまま「権威」と「信用」になります。薄ければ格が落ちる。にじめば疑われる。黒は、刀と同じくらい“効く道具”でした。
奈良という土地は、都が移っても「書く現場」が消えませんでした。東大寺、興福寺、元興寺といった大寺が残り、写経や記録が日々積み上がっていく。文字は祈りであり、行政であり、学問でもある。その熱量が、奈良墨という文化を育てたと考えると腑に落ちます。墨は文房具ではなく、文明のインフラだったわけです。
古梅園の由緒を語るとき、しばしば名前が挙がるのが松井道珍(まついどうちん)です。16世紀末、戦国の空気がまだ濃いころに良質の墨を生み出し、奈良墨の評価を押し上げた人物として伝えられています。戦国は、刀だけの時代ではありません。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった権力者は、命令や外交のために大量の文書を出しました。大名の朱印状、寺社の由緒書、商人の手形。紙の上で天下が回るほど、黒の質は問われます。
そして忘れてはいけないのが、宮中の「書」の系譜です。和歌、勅書、綸旨、儀礼の記録。そこでは墨色の品格が、そのまま作法の一部になります。たとえば光格天皇のように宸翰(しんかん)で知られる存在もいて、宮中にとって書は芸事であると同時に、文化の骨格でした。だからこそ、奈良墨が宮中や寺社の書の世界で重んじられてきたのは自然な流れで、その延長線上で古梅園の黒も「御用墨」として語られてきます。黒は裏方なのに、なぜか消えない。ここがいちばん面白いところです。
明治になると、鉛筆やインクが広まり、文字は一気に工業製品になります。それでも墨は消えませんでした。書は芸術になり、写経は修行として残り、日本画は墨の濃淡で空気を描くようになる。時代が変わっても、古梅園が作り続けてきたのは「最短で心に届く黒」だったのだと思います。急がない黒。落ち着かせる黒。手を動かす人の呼吸に、黙って寄り添う黒です。

出典:古梅園
工房は、時間の配置図。
古梅園の面白さは、商品だけではなく「場所」にもあります。奈良町の椿井町あたりに、店舗、工場、土蔵、住まいがまとまって並ぶ。ここは、いわば墨づくりの流れそのものが、建物の配置になっている場所です。墨は「製品」ですが、同時に「時間」でもある。乾かす、寝かす、磨く。焦っても、良い黒にはなりません。だから古梅園の黒には、急がない強さがあります。書き急ぐ手を、いったん止めてくれる黒です。
工程を思い浮かべてみると、さらに腑に落ちます。松の煙から煤を集め、膠で練り、型に入れ、乾かし、最後に磨く。工房には採煙蔵、銅壷場、細工場、灰替所、編み場、磨き作業所など、工程ごとの場が用意され、仕事の順番通りに空気が流れます。墨は、途中で近道できない。だからこそ、完成した黒に「余計な焦り」が混ざらないのです。

出典:古梅園
煤(すす)と膠(にかわ)が、黒に骨を入れる。
墨の材料は、驚くほどシンプルです。煤(すす)と膠(にかわ)。煤は、松の煙などから集めた微細な粒で、黒の色そのもの。膠は、動物性のたんぱく質由来の接着成分で、粒をまとめ、紙に定着させ、線に「芯」をつくります。この二つの配合と熟成が、黒の性格を決めます。
たとえば、同じ黒でも、濃くすれば沈むように暗い。薄めると、青みや紫の気配がふっと立つ。黒は一色なのに、表情が多い。これが、墨の面白さであり、古梅園が追い求めてきた「黒の奥行き」です。デジタルの黒は均一ですが、墨の黒は生きものみたいに揺れる。その揺れが、書や絵の呼吸になります。

出典:古梅園
固形墨と墨液、どっちが正解?
初めて古梅園を選ぶ人が迷うのが、固形墨(墨)か、墨液か。結論から言うと、用途で決めるのが正解です。書道や写経で「線の表情」を出したいなら固形墨。すり具合で黒の立ち上がりを調整できるからです。いっぽう墨液は、忙しい日や制作の下描きで頼りになります。一定の濃さで出せて、準備の時間が短い。最近はデザインや建築のスケッチで墨液を使う人も増えています。
ただ、固形墨には固形墨の「贅沢」があります。黒を起こす時間そのものが、心のストレッチになる。墨をすっているうちに、頭の中のノイズが落ちていく。古梅園の墨が「道具以上」だと言われるのは、この体験まで含めての価値があるからです。

出典:古梅園
黒は、使うほどにやさしくなる。
良い墨ほど、使い込むほどに「当たり」が出ます。すりやすくなり、香りが安定し、黒が落ち着く。黒の世界は、派手な進化ではなく、静かな馴染みです。ふと手を止めたとき、硯の上の黒が、ただの色ではなく「深さ」になっている。古梅園の墨は、そういう瞬間が多い。
贈り物としても優秀です。墨は、年齢や趣味で派手に好みが割れにくい。しかも「ちゃんとしたもの」を渡したい場面に強い。書道家や日本画家への贈答はもちろん、最近は大人の趣味として写経や手帳の筆記を始める人も増えています。古梅園という名前が箱にあるだけで、背筋が少し伸びる。黒の贈り物は、相手の時間を尊重する贈り物です。

出典:古梅園
墨は、時間を描く。
すった瞬間に立つ香り。筆が紙に触れ、静寂の中に線が走る。その一瞬に、過去と現在が重なります。寺の写経も、戦国の書状も、学者の書き付けも、最後は黒で残る。古梅園の墨は、その「残り方」がきれいです。濃淡に表情があり、線が痩せず、余白を濁さない。黒で、心が整う。そんな体験を、千年単位の書く文化の延長線上で、いまの私たちに手渡してくれます。



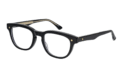
コメント